
教育虐待って何?

教育虐待とは、「教育」を口実に、親が子供を心理的に追いつめたり、果ては身体的な暴力をふるったりすること。
教育虐待とは
教育虐待とは、「教育」を口実に、親が子供を心理的に追いつめたり、果ては身体的な暴力をふるったりすることを指します。虐待という言葉からは過激な印象を受けますが、もっと広範に不適切な関わり全般を含む概念です。
まずは『「勉強しなさい!」エスカレートすれば教育虐待』(レビュー)に掲載された専門家(小児科医 古荘純一氏)の発言を引用します。太字は原文のとおりです。
「親がどんな意図で行っているかは関係ありません。いくら『子どもの将来のため』といった、子どもを思う気持ちが前提にあったとしても、教育を強いる親の行為が子供の受忍限度を超えており、子どもにとって有害であれば、それは教育虐待といえます。(略)」
「勉強しなさい!」エスカレートすれば教育虐待――中学受験させる親 必読!
それでは「教育虐待」と「教育」の境目は、具体的にどこにあるのでしょうか。以下は被害者の体験談『父の逸脱――ピアノレッスンという拷問』(原著はフランスで発行。レビュー)に、児童精神科医ダニエル・ルソー氏が寄せた解説からの引用です。
(略)いったいどのあたりから暴君になり、育てるとは正反対に若い芽を摘むことになるのか。
父の逸脱――ピアノレッスンという拷問(「原書解説」より)
親はしばしば基準を見つけることによって、その回答を見いだそうとする。すなわち、何時間くらいまでなら、何歳からなら、という回答である。しかしながら、答えは子どもの様子にある。子どもは楽しいと感じているか、子どもは嫌だと言っていないか、子どもはなんと言っているのか、どう思っているのか。
本の中にある教育虐待についての説明を、箇条書きで挙げます。
- 「虐待」という言葉の響きは強烈だが、意味合いとしては不適切な扱い(mal-treatment、マルトリートメント)も含む
- 言葉や態度(ため息等)、表情、視線などで心理的に追いつめるだけでなく、殴る・蹴るなどの身体的暴力を伴ったり、食事や睡眠を制限するケースもある
- 学業だけではなく、習い事で行われる教育虐待もある(音楽やスポーツのエリート教育など)
- 学齢期前の子供も教育虐待の対象になり得る
なお、教育虐待について取り上げている本の一覧は、以下の記事をご参照ください。
特徴
教育虐待ならでは特異性を述べている部分を引用します。
子どもの虐待問題は貧困などと密接に結び付きやすく、社会的な支援が必要な家庭で起きるケースが少なくありません。しかし、同じ虐待といっても「教育」虐待の場合、経済的に余裕があり、何の問題もないように見える恵まれた家庭で起きるケースが少なくない、と複数の専門家が指摘します。
武蔵野大学教授の武田信子さんによると、教育虐待に走りがちな家庭には、
- 両親共に高学歴で社会的地位が高い
- 親が経済的事情などでかつて進学を諦めた
- 母親がキャリアを捨てて専業主婦になった
- 家庭の中で母親だけ学歴が低く、夫の親族から重圧を感じている
といった特徴があるそうです。
「勉強しなさい!」エスカレートすれば教育虐待――中学受験させる親 必読!
またシンプルに教育上の問題があるだけでなく、家庭内の別の問題と組み合わさると、事態はもっと複雑になります。この点については色々な本で言及されていますが、2か所だけピックアップします。
しかし教育虐待の闇には、もっと根深い問題が隠れていることがある。親が育った家庭環境に起因する家族の機能不全が根本に潜んでいる場合だ。
ルポ 教育虐待
夫婦間でコミュニケーションが取れていないことが、教育虐待につながることもあるようです。「もともと夫婦間が非常に不仲で、家庭の中での緊張が強いという状況は、それ自体が子どもにとっては心理的虐待といえます。そこにきて、夫婦で教育方針が異なり、それぞれが子どもに、自分の方針に従うように強要したりすると、教育虐待になります。子どもは、どう対応していいか分からず混乱してしまいますよね」(古荘さん)
「勉強しなさい!」エスカレートすれば教育虐待――中学受験させる親 必読!
語源
「モラハラ」は『モラル・ハラスメント――人を傷つけずにはいられない』(レビュー)、「毒親」は『毒になる親』(レビュー)という本のタイトルから広まった用語であることは知られています。では「教育虐待」という用語は、どのような生い立ちなのでしょうか。
「教育虐待」はメイド・イン・ジャパンの用語です。詳述している『ルポ 教育虐待』(レビュー)から関連の記述をピックアップし、分かりやすく並べました。なお文中の「カリヨン子どもセンター」とは、子どもが家庭から逃れて入所することができる子どもシェルターのことです。
- 最初期関係者の間で俗語的に「教育虐待」という用語が使われる
「教育虐待」という言葉はもともと、「カリヨン子どもセンター」のスタッフの間で「あの親は、教育という名のもとに虐待しているよね」というような文脈で俗語として使われていたものだ。それを埼玉大学の岩川直樹教授がヒアリングし、武田さんに伝えた。
- 2011年12月初めて公に「教育虐待」という言葉が登場する
鈴木さんの記事によれば、教育虐待という言葉が初めて公に使われたのは2011年12月。「日本子ども虐待防止学会 第17回学術集会いばらぎ大会」で武蔵野大学の武田信子教授が、「子どもの受忍限度を超えて勉強させるのは『教育虐待』になる」と発表した。
- 2012年8月「教育虐待」が新聞記事になる
「カリヨン子どもセンター」の取り組みを知って、2012年8月、それを記事にしたのが毎日新聞の記者・鈴木敦子さんだった。「教育虐待 勉強できる子になってほしい……過剰な期待」という記事を書いた。
まとめ
教育を強いる親の行為が子供の受忍限度を超えており、子どもにとって有害であれば、それは教育虐待










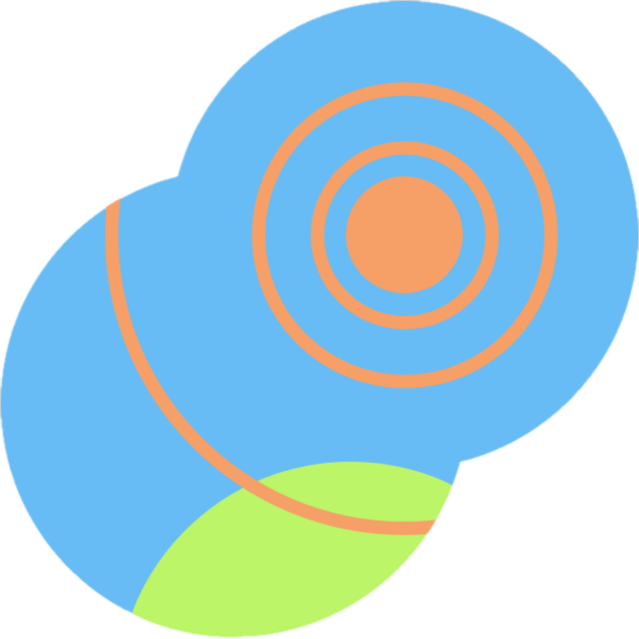
コメント