★★★★★
受験・進学を念頭に行われる教育虐待について、豊富な取材をベースに数々の実例を紹介。親の心理や、家族や社会の背景にも迫る。
なかなかヘビーな我が家の教育虐待の状況にマッチする内容だった。
レビュー
本の目的・内容
教育ジャーナリストのおおたとしまさ氏の著書です。本の中で「教育虐待の闇を照らす。これが本書の目的だ」と述べています。
「ルポ」というタイトルが示すとおり、本の前半は実際に著者が取材した実例で占められています。
取材は広範かつ綿密に行われているように感じました。教育虐待を受けて成長した人だけでなく、教育虐待をした親、その周辺にいた人などからも丹念に話を聞いています。また塾の講師・経営者や、子供シェルターの運営者の話も掲載されています。シェルターと言えば、女性(妻)向けのものが思い浮かびますが、子供が単独で家庭から逃れられるシェルターがあることを、私はこの本を読んで知りました。
本の後半では、取材の内容を交えながら「教育虐待」という言葉の生い立ちや、教育虐待を引きおこす親の心理、家族や社会の背景に迫っています。最終章は「第8章 結局のところ、親は無力でいい」です。
この本では単に教育が行き過ぎてしまったケースだけでなく、深刻な事例も取り上げています。「家族の機能不全」に踏み込んでいる部分を引用します。
親自身が自分の人生のなかで解消できていない恐怖心、孤独な子育てのストレスや夫婦間の葛藤などの要素が加わると、「あなたのため」という言葉はもはや呪いとなり、子どもを壊す教育虐待にまで発展することがある。
ただし、単に教育熱心の度がすぎてこれらの悪条件が重なっただけであるのなら、そこから抜け出すのは不可能ではない。(略)
しかし教育虐待の闇には、もっと根深い問題が隠れていることがある。親が育った家庭環境に起因する家族の機能不全が根本に潜んでいる場合だ。
なお、前著に『追いつめる親――「あなたのため」は呪いの言葉』があります。『ルポ 教育虐待』は、この『追いつめる親』に「大幅な加筆・修正を施したもの」です。
私は先に前著に目を通していたのですが、その時に感じたひっかかりがなくなり、すっきりと読みやすくなっていました。またタイトルに「教育虐待」「毒親」というキャッチーな単語が入って、困っている人に届きやすくなったと思います。
感想・私見など

我が家の状況はモラ夫から上の子に対する教育虐待じゃないかと、うすうす感じていましたが、この本の内容は我が家の状況を言い当てていました。
特に親が子供を追いつめていく際の具体的なやり取りのパターンがモラ夫のやり口とそっくりで、背筋がゾッとしました。
著者は名門校と言われるような中学・高校の受験絡みの著書を多数上梓しています。いやらしい見方をすると、受験熱が高まれば高まるほど儲かるはずですが、それに逆行する方向へ警鐘を鳴らしているわけです。また、この本の中に登場する進学塾の関係者も同様に、経営面からは好ましからざる危機感を持っていることが分かります。我が家だけでなく社会全体でヤバいことになっているのではないかと感じました。
この本には、気付きを得て教育虐待から抜け出した事例も登場します。自身が教育虐待を行っているのではないか、あるいは夫・妻のやっていることは教育虐待ではないか、と心配な方に一読をおすすめいたします。子供にとって良い方向へ舵を切るきっかけになります。
なお、うちはそこまで深刻ではない、と思う方には、以下の本のほうが読みやすいかもしれません。
まとめ
豊富な取材に基づき、受験・進学を念頭に行われる教育虐待の実例や、親の心理、家族や社会の背景を詳らかにする。
★★★★★ (なかなかヘビーな教育虐待が行われていた我が家にマッチする内容だった)
- 追いつめる親――「あなたのため」は呪いの言葉










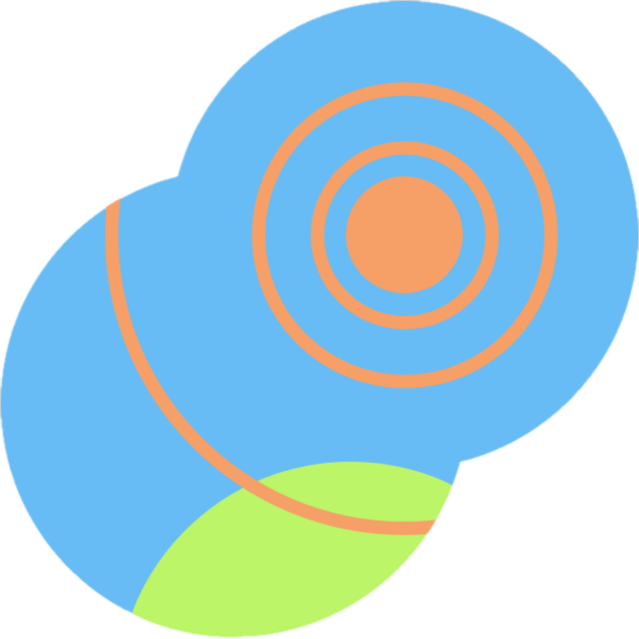
コメント