★★★★★
DV加害者へのカウンセリングの手法を解説。
DVを行うパートナーや自分自身を変えたいと思う方へ。
レビュー
本のあらすじ・位置づけ
この本は、被害者ではなく加害者へのアプローチに主眼を置いて、DV問題を解決することを目指しています。著者(カウンセラー)は従来のカウンセリングの手法を採用しつつ、さらに独自に臨床・研究を重ねてブラッシュアップを続けています(現在進行形)。本の中ではその方法を紹介。
カウンセリングは相談者ごとに年単位・月単位で、段階を経て実施されます。さまざまなステップの中から、私の印象に残ったものをひとつピックアップします。
著者はまず、加害者像について、次のように述べています。
DV加害者のほとんどに共通していることは、彼らはパートナーや子どもに対しては加害者であるが、生い立ちの中では彼らもまた暴力的なことを受けてきた被害者であるということである
その上で、DV加害者が親(毒親ですね)に対して抱いている怒りを正しく認識し、その怒りをパートナーではなく親に向けるよう説いています。関連の記述をいくつか引用します。
「(略)大いに親のせいにしましょう。ああいう暴力を振るう親に育てられたから、自分も妻に暴言暴力を振るうようになったんだと思ってもいいんですよ」
こう言うと、多くのDV加害者は涙ぐんだりする。また、そうだったんだーと納得のいく顔をしたりするのである。初めて謎が解けたというような顔をする人もある。
DV加害者の正夫さんは、妻への激しい怒りの根っこに、父親から受けた激しい体罰への怒りや恨みがある、ということがわかってから、怒りの矛先が少しずつ変わっていった。
私も彼に、「あなたの怒りやすさの根っこには、父親に殴られたことへの怒りがある。その怒りをあなたを殴った父親に向けるならわかるけれど、妻に向けるのは全くのお門違いではないか」とか、「怒りは本来向けるべき人に向けないと、パートナーや子どもなど、向けてはならない人に向けてしまうことになってしまうんですよ。だから、これからは、お父さんに言いたいことをちゃんと言えるようにしていきましょう」ということを言ってきた。
なお、女性のDV加害者についても章立てして扱っている(第5章)点が、DV本の中でも特徴的です。
目次は次のとおり。
- まえがき
- 第1章 絶えないDV問題……その深刻な実態
- 第2章 DV加害者は変われるか? なぜ変わらないと思われているのか?
- 第3章 DV加害者を前に立ち往生!
- 第4章 DV加害者カウンセリングを実施して ~ある男性DV加害者の場合~
- 第5章 ある女性DV加害者の場合
- 第6章 DVにつながる心の傷(トラウマ)
- 第7章 DV加害行為の克服に向けて
- 第8章 DV加害者更生カウンセリングでの問題点
- あとがき
本の選定理由・感想等
DVを主題としたこのサイトで、『立ち直りへの道』の書評(レビュー)を掲載した理由は、主に2つあります。
ひとつ目は、被害者ではなく、加害者にアプローチする手法を取っているから。
私にはモラハラ夫がいました(離婚済み)。色々な支援を受けながら(相談体験)、2人の子供を連れて遠方へ別居しました。被害者である私や子供たちのほうが環境を変えねばならないのって理不尽だ! 変わるべきは、モラハラ夫なのに!
もうひとつの理由は、そのモラハラ夫が自分を変えたいと思ったと仮定して、一番効き目がありそうなのは、この本で書かれているカウンセリングのアプローチではないかと感じたため。有効だと思ったポイントはいくつかありますが、とりあえず一つ挙げます。自分が毒親の被害者だと認識するところから始めるのは、被害者意識が強いモラハラ夫にはぴったりではないかと。耳の痛いことを言われたら、カウンセリングに通えなくなっちゃいますから。
一方で、モラハラ夫に共感してばかりでは、モラハラ夫は気分よく通えるかもしれませんが、DV問題を改善する糸口はつかめません。この難しいポイントについて、著者が悩み、考えた内容が、カウンセリング手法に反映されています。
なお、私とは別の立場で、パートナーや子供へ暴言・暴力を振るいたくはないのに振るってしまう方にとっても、読みやすい本だと思います。まずもって、タイトルにある「立ち直り」という単語が優しい。
ぜひご一読ください。
また、以下の記事には「加害者にフォーカスを合わせたDV本」の一覧表を掲載しています。よろしかったら併せてご確認ください。
まとめ
DV加害者へのカウンセリングについての考え方や手法などを解説
★★★★★











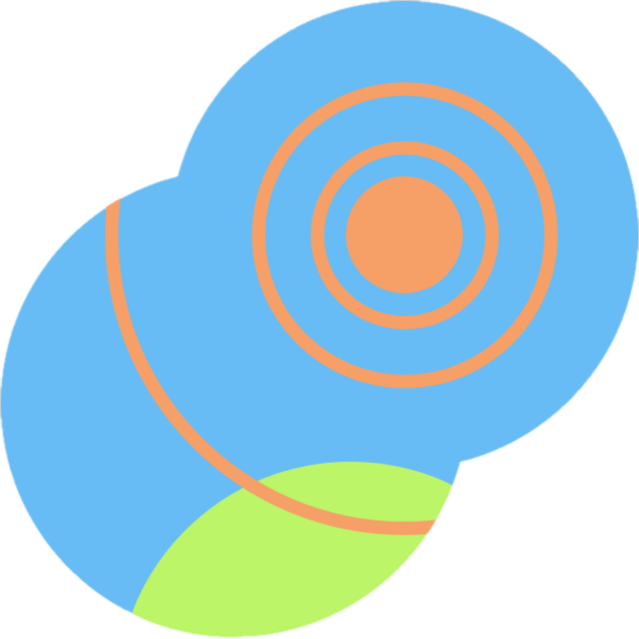
コメント