★★★★★ ロングセラー
虐待の基本「不健康で過剰なコントロール」に関する解説が秀逸。
『毒になる親』と同様に社会にインパクトを与えた本。
レビュー

私自身の両親は、完璧ではありませんが「毒親」には当てはまりません。
私は「毒親じゃないほうの親(母親)」の立場でこの本を読みました。我が子への将来に渡った影響を知りたいと考えていました。
この本は、子供を主に心理的に虐待をする親を取り上げた毒親本です。主要部分は次の3部構成になっています。
- パート1 こういう親が子供を不幸にする
- パート2 問題をよく理解しよう
- パート3 問題を解決しよう
最初のパートでは、不健康で過剰なコントロールについてタイプ別に解説します。パート2ではさらに深堀して、コントロールが成就するメカニズムの紹介があります。最後のパートはいわゆる「毒親の棄て方」です。ただし絶縁のみを意味しているわけではありません。
この本では「コントロールをする親」という表現が頻出します。虐待をする親の中にコントールをするタイプや、別のタイプがいるわけではありません。「コントロールをする親」こそが子供を虐待する親で、子供を不幸にする親です。本の中では次のような説明があります(太字は原文ママ)。
不健康で過剰なコントロールをする親には共通する要素があります。それをひと言でいえば、次のようになるでしょう。
「不健康で過剰なコントロールをする親」とは、子供の成長をはぐくむためではなく、自分(たち)を喜ばせ、自分(たち)を守り、自分(たち)のためになるように行動する親をいう。
ひるがえって我が家で起きていることを眺めると、本に書かれた状況がバンバン出てきました。たとえばモラ夫が無自覚に子供をマインドコントロールしようとしているように、私には見えていました。この本では「洗脳」という言葉を使って、そうした状況の解説がありました。
私はモラ夫と子供達の関わりを間近で見てはいましたが、当事者ではありません。そのために、この辺りは当事者の方々よりも理解しやすかったかも、と思っています(嬉しくないけど)。
読後は、このまま座視していたら、私もモラ夫とは別のタイプの毒親、この本で言うところの「自分の子供を守れない親」になってしまう、いやもしかしたら片足をつっこんでいるかも、と危機感を抱きました。

我が家では、子供たちは父親(私にとってはモラ夫)に息苦しさや恐怖を感じていました。私は「子供たちが成長したら、父親を棄てたいと思うかもしれない」と考えることがありました。
結局のところ今は離婚済みなのですが、それを後押しした理由のひとつが、この本を読んで湧き上がってきた考えにあります。
「私がモラ夫と離婚するのはまあまあ大変だけど、将来的に我が子ちゃんが父親を棄てるよりもずーーーっと簡単」
なお、毒親育ちの方でこの本を読まれる方がいらっしゃいましたら、冒頭の著者のメッセージ(文庫本12ページ)に目を通してください。精神状態が不安定になる場合があることや、それが深刻な場合には資格のある心理セラピストに相談することを伝えています。
また私と同様に親の立場の方にとっては、親視点ではなく子供視点で書かれているために、なかなか読みづらいです。しかし子供のためになる気付きを確実に得られます。気になる状況であれば、ぜひご一読ください。
本の位置づけ
毒親本で一番有名なのは「毒親」の語源となった『毒になる親』でしょう。この『不幸にする親』はそれと対で語られることがあります。「訳者あとがき」にある、この2つの本の位置づけに関する説明がとても分かりやすかったので、ここにまとめます。
| 毒になる親 一生苦しむ子供 | 不幸にする親 人生を奪われる子ども |
|---|---|
| スーザン・フォワード著 1989年発行(原著初版) | ダン・ニューハース著 1998年発行(原著初版) |
|
|
まとめ
親から子供への精神的虐待「不健康で過剰なコントロール」についての解説の後、問題の解決方法を提案。
★★★★★ (「虐待しないほうの親」の立場で読んで、さまざまな気付きが得られた)








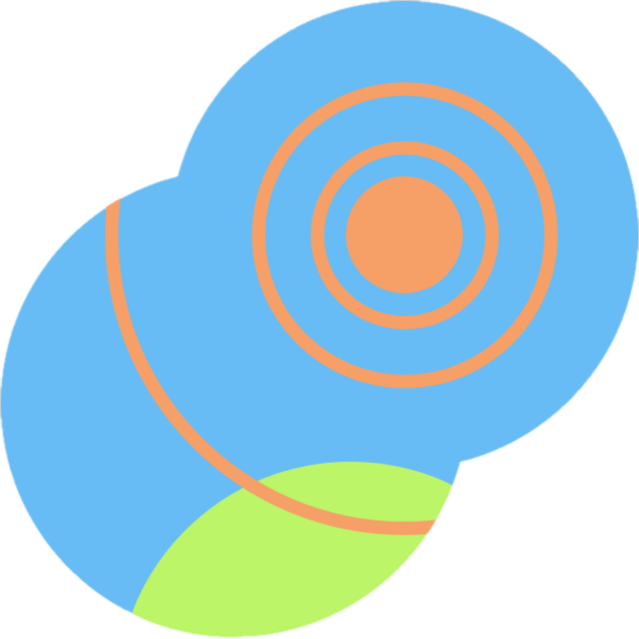
コメント