★★★★★
臨床経験豊かな精神科医が、ケーススタディを通じて、大学病院の精神科の診察室の様子や、訪れる患者の背景を語る。
精神科の実態を垣間見られる。
レビュー
この本では、ケーススタディを通じて、大学病院の精神科の診察室でのやり取りや、精神科医の頭の中・心の声を詳らかにしています。取り上げている症例は自己愛性パーソナリティ障害、境界性パーソナリティ障害、統合失調症、妄想性うつ病、双極性障害などなど。
著者は「臨床に携わっているのは17年ほど」の精神科医(執筆時点)。「文庫本あとがき」で対象読者について「多くの人に読んでもらいたいのはもちろんだが、医学部や看護学部など医療福祉系の学部を志望している若者に、ぜひこの本を手に取ってもらいたい」と述べています。
難解になりそうなところですが、読み物のようにすらすらと読めます。差し挟まれているエピソードには、医者と患者だけでなく、病院職員や家族も登場。精神科医の悩ましさや家族の苦悩なども率直に語られています。なお「真正さと正確性を土台にしているものだが、(略)個人のプライバシーを守ることを優先させている」との断り書きがあります。
このWebサイトのテーマであるDV・モラハラ・虐待を軸に話が展開するわけではありませんが、自己愛性パーソナリティ障害や境界性パーソナリティ障害の事例の中に、そのエピソードを確認できます。
またモラハラ夫は病気なのか、DV夫は異常なのか、と妻の立場では悩むかもしれません。その判断を下すのは、医者であってもなかなか難しい様子が本に描かれています。
自己愛性パーソナリティ障害(Narcissistic Personality Disorder、NPD)を引き合いに、診断の難しさを述べている部分を引用します。
単なるわがまま、自分好きと、「障害」の違いは、何なのであろうか。ナルシシストは(略)、外面は、最初だけはえてして良いものである。正常範囲のナルシシストと、障害・異常レベルのナルシシストは、どう区別するのだろうか。実はこの問題は、精神医学が今もって解決できない課題である。
古典的な「パーソナリティ(以前は人格)障害」の大まかな定義は、パーソナリティ(人格)の異常な偏りによって、本人が苦しむ、ないし周囲が困るという曖昧なものだ。今もこの曖昧さは変わらず、NPDの診断基準を見ても数値など客観的指標は乏しく、解釈次第ではいくらでもあてはまる人間はいるように思えてくる。
この本には「うちのモラハラ夫は自己愛性パーソナリティ障害なんじゃないか」などと思う方や、あるいは精神科やメンタルクリニックに訪れるかどうか悩んでいる方に、役に立つ情報が載っています。ぜひご一読ください。
まとめ
ケーススタディを通じて、大学病院の精神科の診察室でのやり取りや、精神科医の頭の中・心の声を明らかにする。
★★★★★ (秘密のベールに包まれた精神科の実態を垣間見られたような気がした)









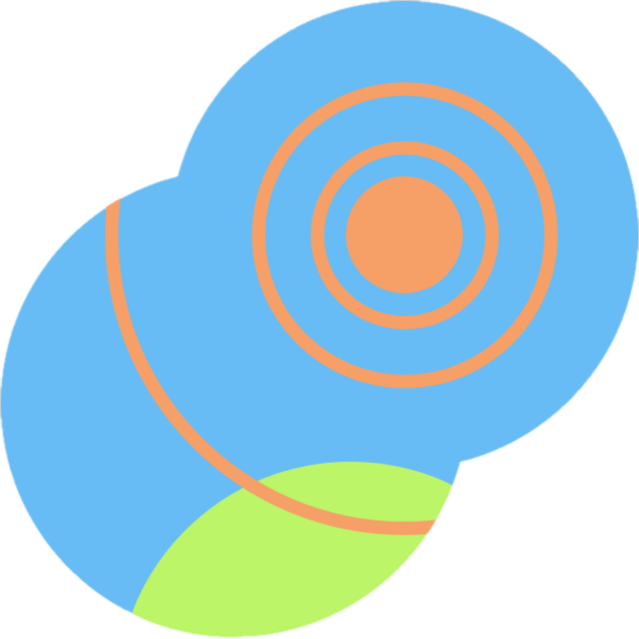
コメント