★★★★★ ロングセラー
DV家庭で育つ子供(小学生)に「ひとりぼっちじゃないよ」と語りかけて、相談先を案内する。
父親(母親の恋人)がDV加害者として描かれており、そのようなパートナーを持つ母親が、子供の気持ちを理解し、対処法や相談先を知るのにも役立つ。
レビュー
この本は、学校(おそらく小学校)に通う子供たちを軸に話が展開します。「わたし」という一人称を使って、子供が自分の家庭環境や気持ちを吐露します。特定の1人を取り上げているわけではなく、複数のケースが想定されています。挿絵には女の子も男の子も登場します、
著者はその子供に「あなた」と呼びかけながら、「ひとりぼっちじゃないよ」と語りかけ、信頼のおける誰かに相談するように再三促します。
誰かに伝えてみてごらん。
もし、あまりうまく言えそうになければ、
この本を誰かに見せて、「この子はわたし」って言ってもいいんだよ。
子供の視点で、家庭環境や子供の気持ちが表現されています。すべての漢字にルビが振られていますが、「残酷」「法律」「違反」「権利」「影響」など難しい単語が使われています。高学年ならひとりで読んで理解できるかもしれませんが、低学年の子には解説が必要だと思います。
本の後ろのほうに「どこに助けをもとめればいいの?」と題して、相談先のリストが掲載されています。先生、祖父母、母親、友達の両親、スクールカウンセラーなど身近な大人から、行政・警察など公的な相談窓口まで紹介。
小学生向けの類書はほとんどないので、その点で非常に意義のある本だと思います。大人であっても自分がモラハラやDVの被害にあっているとは気付きにくいし、認めにくいと言われています。子供のほうが自分の家族がおかしいとは思いづらいので、気付きが得られるはずです。
ただ、すべてのDV家庭の子供にこの本がマッチするかというと、なかなか難しいと思います。この本のおおまかなストーリーは、父親(または母親の恋人)がDV加害者で、母親とシェルターに避難したのち、新しい土地・新しい学校で生活を送る、となっています。これと合わないケースもあるでしょう。
また、自分の置かれている状況がおかしいとは思っていない子供に、誰かがこの本を差し出したら、子供はショックを受けるかもしれません。たとえばカウンセリングルームに置いてあって、子供が自ら手に取るような読み方が、ふさわしいように思います。
念のためお伝えいたしますと、本の64ページに大人がこの本を利用して子供と接する際の注意事項が記載されています。

私は子供には渡さずに、自分が読むのに留めました。
まだモラ夫と同居している頃、私にとっては別居生活は明るい未来でしたが、子供達が未知の生活・転校・転園に希望を抱くとは思えませんでした。
また実際に、シェルターに避難してから別居生活を始めたのですが、その計画は子供達には秘密にしていたので(モラ夫にバレないように)、別居前にこの本を渡すわけにはいきませんでした。
父親の所業が、本とは違う面が多かったのも理由のひとつです。
この本の第一の想定読者は子供ですが、私は母親の立場で読んで、子供の気持ちの一端が分かりました。実際のところ、DV家庭で生活している小学生の心理についての分かりやすさで言えば、随一の本だと思います。子供向けに書かれているので、簡単に読めました。私としては、子供より、その母親の立場の方におすすめいたします。
まとめ
DV家庭で育つ子供(小学生)に「ひとりぼっちじゃないよ」と語りかけて、相談先を案内する。
父親(または母親の恋人)がDV加害者で、母親とシェルターに避難したのち、新しい土地・新しい学校で生活を送る、というストーリー。
★★★★★ (母親の私が、小学生の子供の気持ちを理解するのに役立った)







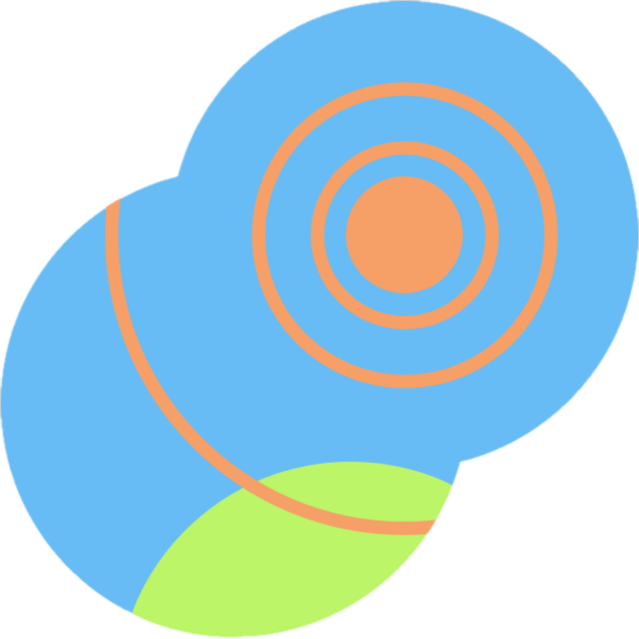
コメント