★★★★★
家のモノが突然壊れたら、業者に頼むしかない?
この本は家庭にあるモノを自分で修繕・修理の方法を掲載。臨時出費を抑えられます。
レビュー
本の構成・あらすじ等
この本では、家の設備や家庭用品をホームセンターで入手できる工具&材料を使って、補修・修理する方法を解説しています。取り上げているのは、以下の4つです。
- 水回り(水漏れ、トイレ、等)
- 住まい(壁紙、柱、カーペット、障子、網戸、等)
- 身のまわり(プラスチック、傘、等)
- 自転車
図解はすべて写真ではなくイラスト(線画)を使用。重要ではない部分の視覚情報が削ぎ落され、必要な線だけを視認できます。本の副題にあるとおり、確かに分かりやすかった!

実は、別居前から『なんでも自分で修理する本』の古いバージョン(水色の表紙、2008年発行)を持っていました。モラな元夫は大工仕事っぽいものも含め家事全般をやらないタイプ。そして私はそれを助長するタイプだったために、この本には大変お世話になりました。
しかし別居時に持ち出すのを忘れちゃったんです……。本棚ではなく工具置き場に置いていたのが原因でした。別居後に本屋で面陳列されている新本(紺色の表紙)を見かけ、即買いしました。
(面陳列:表紙を見せる展示の仕方)
旧本にはなかったコンテンツ(以下)が追加され、本の厚みが増しています。
- 工具の選び方・使い方の解説
- 消毒・紫外線殺菌(新型コロナ対応)
感想
私はこの本を読んだだけで、家のモノを自力で修理することへの心理的なハードルが下がりました。やり方が分からないので躊躇していましたが、分かってしまえば「意外と簡単そう」と思ったものがチラホラ。
それに世の中って、進歩しているんですね! 便利ツール・便利グッズが出ているんですよ! 伝統的・正統なやり方では難易度が高くても、新しいグッズを使えばできそう。
たとえば私が子供の頃、母は障子を毎年貼り替えていました。小麦粉を溶いて熱して糊を作り、ハケで桟にその糊を塗る、というオールドスタイル。この本には、アイロンで固定できる障子紙が紹介されています。
この本の手順に従えば、女性・男性に関係なく、自分で家の中のモノを修理できるようになります。一度やれば、覚えられる! ぜひ1冊手元において、お金の節約を。
まとめ
家の設備や家庭用品をホームセンターで入手できる工具&材料を使って、補修・修理する方法を解説。巻末特典として、工具に関する説明もあり。
★★★★★ (別居前からお世話になっている)
- タイトル:完全保存版 なんでも自分で修理する本――イラストだからわかりやすく簡単!
- 著者:片桐 雅量
- 出版社:宝島社
- 発行日:2020年7月24日







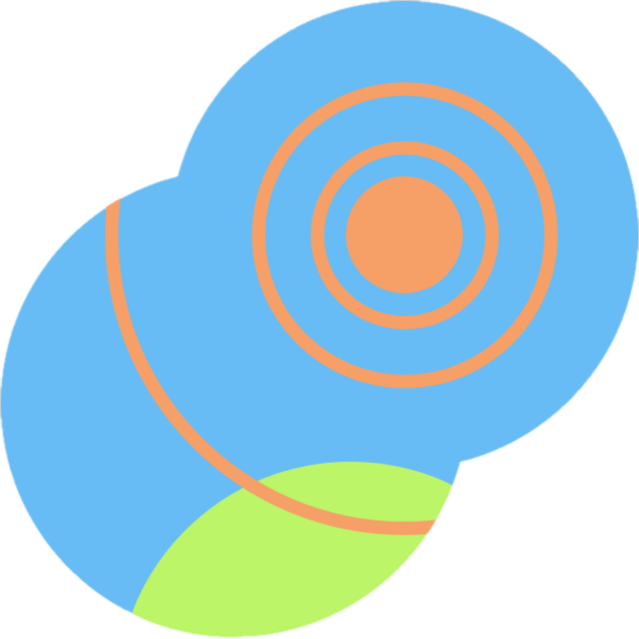
コメント