★★★★★
専門家ではない、学校の先生などの支援者に向けて書かれているので、親の立場でも理解しやすい。
図解たっぷり。
レビュー
この本は専門家(精神科の医師、心理士など)ではなく、たとえば学校の先生や地域の小児科医など子供と関わりがある方に向けて、トラウマを抱く子供の「支援者」になり得ることや、実際の支援の仕方を伝えるものです。また、当事者(子供・親)にとっても「自己理解と回復」にこの本が役立てば、と監修者は期待を寄せています。
「トラウマ」というテーマがテーマだけに、小難しい文章で埋め尽くされた分厚い本だと読むのをためらいますが、この本の作りはまったく違います。二色刷りで図解が多用されています。本をパラパラめくったときのパっと見で、読みやすそうな印象を持ちました。実際に読んだところ、第一印象どおりに理解しやすかったです。専門用語には解説が添えられていますし、長々と文章が続くわけではなく囲み枠や吹き出しで記述内容がきっちりと区分されていました。
内容に触れると、章立ては次のとおりです。
トラウマの原因として、第2章で虐待にフォーカスを合わせていますが、第3章では災害、いじめ、マイノリティであることなど広範に取り上げています。
第4章では、親の立場でも子供のために使える実践的な情報が載っています。子供と話すときの注意点や、子供がしてほしいこと・言ってほしいことが分かります。
第5章は公的な支援についてまとめられています。支援を受ける側に発信された情報では、関係機関同士が裏側でどうつながっているのか分かりにくいですが、この本で舞台裏が垣間見えました。

モラ夫(元)が子供に暴力的で、母親の私が打てる手がないか、ずっと情報を探していました。別居後にこの本が発行されたので、渦中に読むことはできませんでしたが、「あのときにあれば」と思った本のうちの1冊です。
また別居後の今でも、時折、子供たちから気になる言動が発せられることがあります。そんなときにも活用できる情報がありました。
子供が心に傷を負っていないか心配な方(親)におすすめです。
まとめ
子供のトラウマについて、学校の先生などの専門家ではない支援者に、特徴や支援方法を図を交えて解説。トラウマの原因として、虐待、災害、いじめなどを挙げる。
★★★★★ (別居後も使えた)









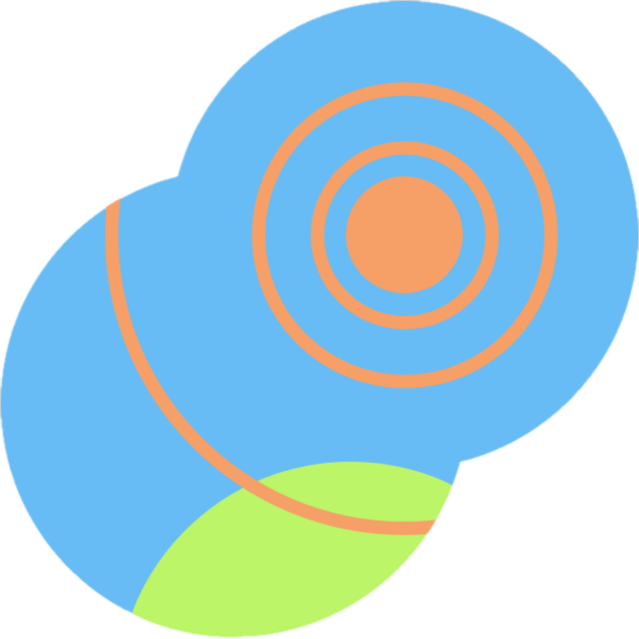
コメント