★★★★★
脳科学の観点を取り入れた毒親本。毒親について分析し(もちろん脳の中身も)、毒親との向き合い方を説く
レビュー
本のあらすじ・位置づけ
脳科学の観点を取り入れた毒親本です。オキシトシンなど体内物質のはたらきに触れたり、脳の構造や反応に関する研究や実験を引用している点が、体験談をつづった本や、精神医学・心理学に依拠した毒親本とは異なります。
著者が本文中で「親たちをむやみやたらと攻撃するために本書を書いたのではありません」と言っているとおり、冷静な筆致で、毒親について分析し(もちろん脳の中身も)、毒親との向き合い方を説いています。
章立ては次のとおり。
- 第1章 子を妬む母
- 第2章 愛し方がわからない父
- 第3章 愛が毒に変わるとき――束縛する脳
- 第4章 親には解決できない「毒親」問題
本の選定理由
著者は脳科学者の中野 信子氏。メディアで見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれません。本の冒頭で「両親とは特筆すべき大きな確執があったわけでもなく、二人ともいたって平凡な人物であったにもかかわらず、それでも子として傷を受けている」と、著者は吐露しています。
親への屈託がある & 専門家が書いた、という2点をもって、このサイトで書評を公開することにしました。
本の内容は単なる知見の披瀝ではなく、読者の心情への配慮が行き届いているように感じます。
そもそも、脳を鍛えるというような能力開発ではなく、毒親というネガティブな分野(?)に脳科学を持ち出して一冊の本にまとめるなんて、おもしろいと思いました。
感想等
毒親に対する負の感情にどっぷりと浸かっているときより(そういう期間があったほうが健全だとは思います)、本の副題にあるように「毒親になりたくない」など、何かを好転させたい気持ちがあるタイミングのほうが、この本の内容をうまく役立てられるかな、と思いました。親に感じる辛い気持ちに関して共感を得られるだけでなく、打開するためのヒントが見つかる一冊です。
タイトルに「毒親」という単語が3回も出てきますが、文章の中で毒親、毒親と連呼はしていません。むしろ、著者は逡巡しながら「毒親」という用語を使っていることが、本のそこかしこから伝わってきました。そして、読者にも次のように使用上の注意を呼びかけています。
毒親、という言葉は、自分の親がそうであったのかなかったのかを判別して、彼らを責めることによって自分の抱えた痛みをいっとき軽くしようとするために使うのではなく、自分の持っている傷がどれほど深く、それを癒していくためには何が必要なのかを知るために使うべきです。
こんな感じで、読者の感情をかき立てるのではなく、事態をマシにする方向へと誘っています。
私は子供たちの父親(私の元夫)が、子供にとっての毒親だと思って、色々な毒親本を読んでいます。将来的に我が子が父親とのあれこれに悩むようなことがあったら、この本は子供に勧める本の1冊です。
よろしかったらご一読ください。
なお、この本は豊かな語彙や言い回しで読み物としてもレベルが高いのですが、子供(未成年者)にはちと難解です。子供向けの本をお探しでしたら、以下をご参照ください。
大人向けの毒親本の一覧は以下。
まとめ
脳科学の観点を取り入れた毒親本。毒親について分析し(もちろん脳の中身も)、毒親との向き合い方を説く
★★★★★ (科学的な根拠が分かる)










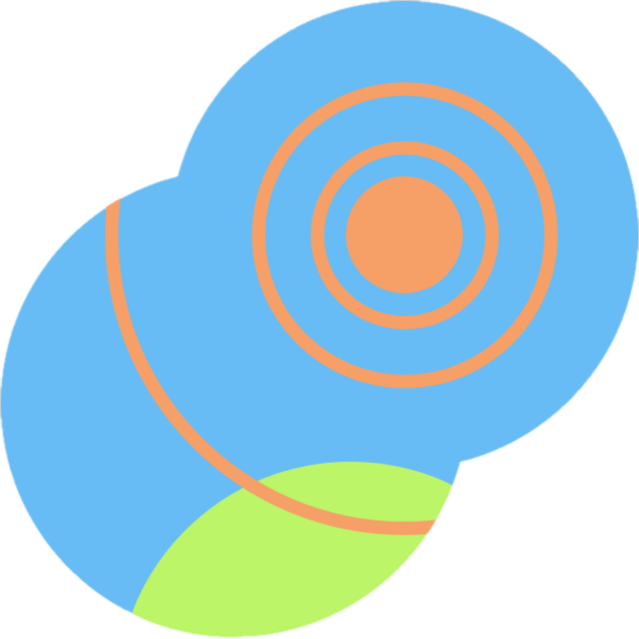
コメント