★★★★★ ロングセラー
過激で派手なサイコパスではなく、家庭や職場など身近にいる「となりのサイコパス」について解説。
我がモラハラ夫(元)が本の中にいた!
レビュー
この本はサイコパスについての解説書です。タイトルにある「良心をもたない人」という用語は、「サイコパス」の意味で使われています。
精神医学の専門家の多くは、良心がほとんど、ないしまったくない状態を、「反社会性人格障害」と呼んでいる。(略)
この良心欠如の状態には、べつの名称もある。「社会病質」、ないしはもっと一般的な「精神病質」。
サイコパスというと殺人鬼のような過激な狂人を連想するかもしれません。しかし、この本で扱っているのは、もっと身近な人物です。著者は「彼らの多くはめだたない」というセクションで、次のように述べています。
ふつうの人は、民族の大量虐殺と、たとえば、会社で同僚について平然と上司に嘘をつく行為とのあいだに、共通点を見いださない。だが、そこにはたしかに、ぞっとするような心理的共通点が存在する。単純だが底が深い共通点。つまり、自分が道徳や倫理に反した行為や、怠惰、利己的と思える行為を選ぼうとしたとき、それを抑えようとする内的メカニズムが欠けているのだ。
この内的メカニズム、すなわち良心をもつかもたないかは、まちがいなく知能程度、民族、性別以上に重要な、人間の本質にかかわるちがいである。
この本ではタイプの違うサイコパスが辿る架空の人生を描写しながら、その精神構造を明らかにしています。サイコパスの家庭・学校・職場における年単位の長いストーリーが語られます。
また普通の人(良心をもつ人)が身近なサイコパスに気づかない理由や、サイコパスの見分け方、サイコパスが生まれる要因などの解説もあります。
著者はこの本を通じて「となりのサイコパス」について警告し、サイコパスに対処するときに役立つ情報を提供しています。
私は数々のモラハラ本やDV本を読んできました。中でも、我が夫(元)の解説として一番しっくりときたのは、この本のサイコパスについての描写です。私の2つの衝撃体験と密接に関係する記述がありました。
1つ目は、長年を経て、ついに「ヤツは自分のやっていることに罪悪感なんて感じていない」と思い至ったアハ体験。本のタイトルを見た瞬間に「罪悪感を感じない」=「良心をもたない」と脳内変換しました。言うなれば、この本全体がそのアハ体験の解説でした。
もうひとつは、モラ夫が子供相手に泣き落としをしているのを目撃した経験です。幼い我が子がモラ夫に同情して慰めており、愕然としました……。翻って、この本の中にもそういう親が登場するのです。しかも、以下のような重大な説明がありました(太字は原文ママ)。
信じてはいけない相手を、どうやって見分けるか。(略) 多くの人は、正体がかいま見えるぶきみな行動や動作、おどすような言葉づかいなどを期待する。だが、私はそういうものの中に、頼りになるヒントはひとつもないと答える。最高の目安になるのは、おそらく”泣き落とし”だと。もっとも頼りになるヒント、平気で悪事をする人びとのあいだでもっとも普遍的な行動は、ふつうの人が予想するように、私たちの恐怖心に訴えるものではない。私たちの同情心に訴えるものなのだ。
他にもこのような点について触れている本はあります。しかし、がっつり取り上げているのはこの本だけでした。
この本はモラハラ夫・DV夫・毒親という観点ではなく、「サイコパス」という切り口で解説をしています。「DV夫=サイコパス」と断定はしていませんが、不気味さをまとった夫も、エピソードの中に登場します。夫のヤバさに心当たりがある方が読むと、ピンとくるかもしれません。よろしかったら、ご一読ください。
なお、2020年12月に「良心をもたない人たち」への対処法を具体化した続編が発行されました。レビューも行っています。ぜひ併せてご確認ください!
| 表紙 | 本 |
|---|---|
 | 良心をもたない人たち 2006年発行(単行本初版) [Amazon |
 | 良心をもたない人たちへの対処法 2020年発行 [Amazon |
まとめ
身近にいるサイコパスの精神構造や見分け方、サイコパスが生まれる理由などについて解説
★★★★★ (本の中にモラハラ夫にまつわる描写がたくさんあった)








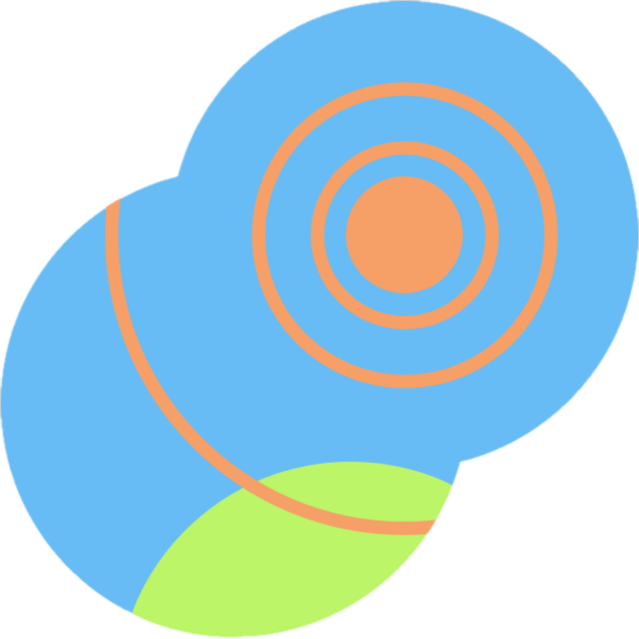
コメント