★★★★☆
普通の家庭ではなく、子供へのマルトリートメント(不適切なかかわり)が行われている家庭の親に向けた育児書。子供の気になるふるまいを列挙し、それぞれに対処例を示す。
レビュー
DVや虐待の本には、子供に悪影響を及ぼす親の行為はた~くさん載っています。では、親は子供にどう接したらいいのでしょうか?
この本では正解例を示しています(あくまでも一例です)。育児本と言えるでしょうが、普通の家庭(?)ではなく、子供へのマルトリートメント(不適切なかかわり)が行われている家庭の親に向けたものです。またタイトルにあるとおり、子供の「脳」への影響という観点から、問題点を指摘し改善方法を挙げています(子供の心理面ではない)。
「マルトリートメント」という単語は「(児童)虐待」という用語の置き換えとして、他の本でも見かけます。ただし両者は包含関係にある概念です。この本から「マルトリートメント」の解説を引用します。
虐待は自分には関係ない。そう思っている人が多いと思います。ですが、たとえば、大きな声で叱ったり、しつけの一環として手加減をしてたたいたりすることはありませんか? このとき、親としては加害の意図はないでしょう。ところが、子どものこころは傷ついています。注目すべきは親の意図ではなく、子どものこころの状態です。子どものこころを傷つけるような不適切なかかわりは、「虐待」という言葉よりも広い意味を持つ「マルトリートメント」と呼ばれ、避けるべき子育てと言えます。
サブタイトルに「マンガですっきりわかる」とありますが、話は文章で進行します。全編がマンガで構成されているわけではありません。とはいえ、読みやすさ・手軽さに重点を置いていることが見て取れます。挿絵的にマンガを多用。図解もたっぷり。文字が大きく、行間が広いので、文章量は多くありません。二色刷りで視認性もアップ。
本は以下の3つのパートで構成されます。
- Part 1 親の言動は、子どもの脳にどのような影響を与えるか?
- Part 2 子どもの脳を傷つけないための39の方法
- Part 3 自分のことも、子どものことも、「ほめ育て」よう
メインはPart 2。子供の年代別・気になる行動別に見開き2ページで、対処法を挙げています。それぞれに一コマ漫画が添えられています。本では計39個の気になるふるまいを取り上げていますが、ここではサンプルとして年代別に3つずつご紹介します。
- 幼児期
- かんしゃくをすぐに起こす
- 親から離れられない
- 人からされたことをネガティブにとらえる
- 学童期
- 落ち着きがない
- ひとりで物事を進められない
- 学力が急に低下している
- 思春期
- 不安、抑うつ
- 完ぺき主義
- 思春期のイライラ
著者は小児精神科医で脳科学者の友田明美氏。他の著書に『子どもの脳を傷つける親たち』(レビュー)や『親の脳を癒やせば子どもの脳は変わる』があります。これらの本は、支援の専門家向けの記述も含まれるなど、少々難解。
ここで取り上げた『脳を傷つけない子育て』のPart 1とPart 3は、この2作それぞれの簡易版といった趣きです。
我が家は私と子供2人の3人家族です。モラハラ夫から逃れてきました。別居してからしばらく経ちますが、子供の言動の中に、以前のモラハラ被害の影響かな、と感じるものも。そうした子供の好ましからざる振る舞いから、対処法を引けるのが、この本の便利なところ。内容がやや物足りないときもありますが、手始めに参照する情報源としてお手軽です。お子さまに気になる振る舞いがあり、モラハラやDVの影響が疑われる場合におすすめいたします。
まとめ
子供へのマルトリートメント(不適切なかかわり)が行われている家庭の親に向けた育児書。子供の気になるふるまいを列挙し、それぞれに対処例を示す。
★★★★☆









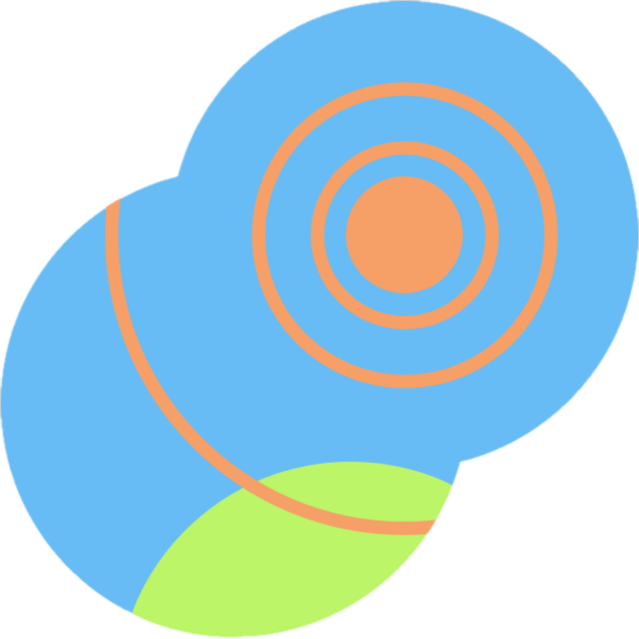
コメント