★★★★★ ベストセラー & ロングセラー
ナチスの強制収容所に3年間収容された心理学者(精神科医でもある)による、人間観察の記録。過酷な環境でも自分を見失わなかった人、他人を助けた人がいた。
人生観が変わる。
レビュー
この本はナチスの強制収容所に3年間収容された心理学者(精神科医でもある)による、人間観察の記録です。悲惨な経験を訴える、単なる体験談ではありません。スポットライトを当てているのは、被収容者(自分や仲間)や監視者(監督やカポー)の精神面です。
本の位置づけについて述べている部分を引用します。
強制収容所についての事実報告はすでにありあまるほど発表されている。したがって、事実については、ひとりの人間がほんとうにこういう経験をしたのだということを裏づけるためにだけふれることにして、ここでは、そうした経験を心理学の立場から解明してみようと思う。
したがって、体験記のように時系列でストーリーが展開していくわけではありません。「収容生活への被収容者の心の反応は三段階にわけられる」として、大まかに「収容」「収容所生活」「収容所から解放されて」の3つの章があります。しかしその中は、心理状態に着目したセクションで区切られています。
著者は1905年にオーストリアのウィーンで生まれたヴィクトール・E・フランクル氏。ナチスの強制収容所で1943~1945年を過ごしました。収容中は知る由もありませんでしたが、両親や妻(新婚)を亡くしています。
この本の意義について著者自身は、被収容者にとっては体験が科学的に解き明かされることにあり、部外者にはその経験や気持ちを理解できるようになることにある、と述べています。
しかしながら『雨と霧』には読者の人生観・世界観にまで影響を及ぼすパワーがありました。単なる収容所生活の記録の域を抜け出して、自己啓発書に分類されるように。なんとなれば英語版のタイトルは、当初は『From Death-Camp to Existentialism』(殺人収容所から実存主義へ)だったものが、『Man’s Search For Meaning』(生きる意味の探求)に改題されました。『7つの習慣』(レビュー)など、数々の名著でもフランクル氏の経験と心理分析が挙げられています。
私はがんじがらめの生活(モラハラ夫によるもの)の中でこの本を読んで、人生観が変わりました。訴えかけてきたのは、過酷な環境でも自分を見失わなかった人、他人を助けた人の逸話です。フランクル氏ひとりではなく他にも、また被収容者にもナチス親衛隊員の中にも、そのような人がいました。
振り返って自分を取り巻く状況を眺めれば、もはや八方塞がりで何も改善するための手立てがないと思い込み、涙を流すことしかできない日々が続いていました。しかしこの本のおかげで、本当に過酷な環境なのか、本当に打つ手なしなのかを自分に問い直す機会を得ました。
いや、若かりし頃に旧版を読んで、感銘を受けた記憶はあったんです。しかし「すごい人もいるもんだな」と、他人事で終わっていました。
この本に「苦しむことはなにかをなしとげること」という短いセクションがあります。私はモラハラ夫に感謝するネタはほとんど持ち合わせていませんが、彼のおかげでやっと様々な人生訓を理解できるようになりました。
この本の厚みはそれほどでもなく、文章量自体は少なめです。しかし、誰が読んでも得られるものがある珠玉の一冊。ぜひぜひお手に取って下さい。
旧版と新版
『夜と霧』には旧版と新版があり、底本も訳者も異なります。
- 1947年原著 旧版 発刊
- 1956年『夜と霧――ドイツ強制収容所の体験記録』発刊(初版)
霜山 徳爾 訳
- 1977年原著 新版 発刊
- 2002年『夜と霧 新版』発刊
池田 香代子 訳
新版の訳者 池田氏は(新版の)「訳者あとがき」において「霜山氏が準拠した一九四七年刊の旧版とこのたび訳出した一九七七年刊の新版ではかなりの異同があった」と述べ、具体的な違いに触れています。
また、2つの版の文体も異なります。(新版の)「旧訳者のことば」から、霜山氏の言を引用します。
あの愚かしい太平洋戦争の絶望的な砲火硝煙の戦場体験を持つ者は、今や七十歳代の終りから私のように八十歳前半までの老残の人間のみである。どうしても骨っぽい、ごつごつした文体になってしまう。(略)
それに対して、新訳者の平和な時代に生きてきた優しい心は、流麗な文章になるであろう。いわゆる“anständig”な(これは色々なニュアンスがあって訳しにくいが「育ちのよい」とでもいうべきか)文字というものは良いものである。
読み比べると、確かに新版は読みやすい! 「訳者あとがき」に「今この本を若い人に読んでもらいたい、という編集者の熱意に心を動かされ、(略)改訳をお引き受けした」とあるのも納得です。高校生でも読めるはず。
しかし、旧版には訳者の並々ならぬ熱意と、原著への誠意・敬意が込められています。実際のところ霜山氏(心理学者でもある)こそが、原著を見出し、日本そして世界に広めた端緒を作りました。以下は(新版の)「旧訳者のことば」からの抜粋です。
西ドイツ政府留学生に選ばれた時には三十歳を過ぎていた。その在独中に著者フランクルの「或る心理学者の強制収容所体験」という粗末な紙の書物に出会い、いたく心をひかれ、邦訳の許しを得るために、私はウィーンに彼を訪ねた。
海外のベストセラーを日本に持ってきたわけではなく、出版当初は売れていなかった「粗末な紙の書物」を日本に紹介しました。
『夜と霧』という邦題も、霜山氏が当てました。新訳版の「訳者あとがき」にて「夜陰に乗じ、霧にまぎれて人びとがいずこともなく連れ去られ、消え去った歴史的事実を表現する言い回し」との説明があります。
旧版と新版は別の書物として、どちらもおすすめいたします。旧版のレビューも、いずれこのサイトに掲載する予定です。
| 表紙 | 本 |
|---|---|
 | 夜と霧 新版 2002年発行。池田訳 [Amazon |
 | 夜と霧――ドイツ強制収容所の体験記録 1985年発行(初版は1956年発行)。霜山訳 [Amazon |
まとめ
ナチスの強制収容所に3年間収容された心理学者による、人間観察の記録。スポットライトを当てているのは、被収容者や監視者の精神面。過酷な環境でも自分を見失わなかった人、他人を助けた人がいた。
★★★★★ (人生観が変わった)







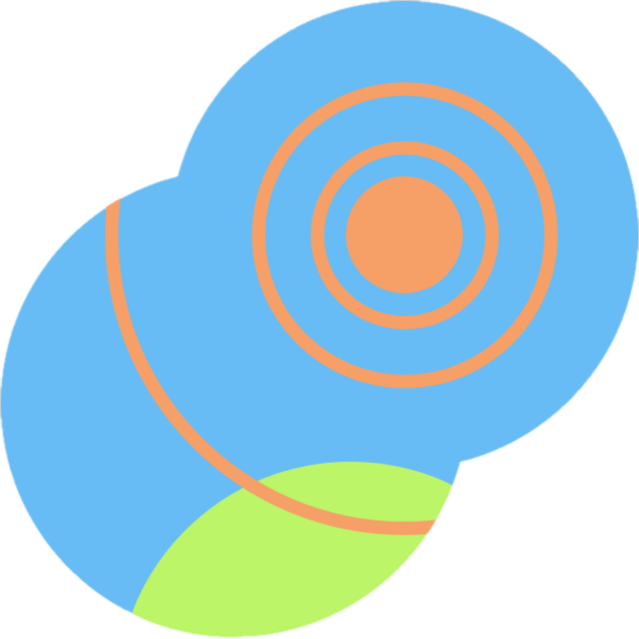
コメント