★★★★★ ロングセラー
他人の心を操ろうとする人を「マニピュレーター」と称し、その特性、手口、対処法を提示する。
教育虐待の事例もあり。
レビュー
この本では自分の意のままに他人の心を操ろうとする人のことを「マニピュレーター」「攻撃性パーソナリティー」と称して、その特性や対処法を解説します。
著者は米国の臨床心理学者ジョージ・サイモン氏。原書の刊行当時(1996年)に信じられていた精神分析法や人間観ではうまく対応できなかったマニピュレーターに関し、独自に研究を行いました。
本の目的について、「はじめに」でイイ感じにまとめられていたので引用します。なお、「気配」を感じ、「手口」を知り、「撃退」する――これが引用箇所のあるセクションのタイトルです。
私がこの本でめざしているのは三つの目的をとげることにある。ひとつは、潜在的攻撃性パーソナリティーの特質とともに、パーソナリティー障害全般について熟知してもらうこと。攻撃性パーソナリティーのさまざまなタイプを見渡したうえで、潜在的攻撃性パーソナリティーが抱えているきわめて特異な性質についてふれていきたい。(略)
二番目のねらいは、潜在的攻撃性の持ち主たちがどのようにして人を踊らせ、関係を操って相手を支配するのか、その点をあますところなく解明する点にある。「潜在的」「顕在的」といったタイプを問わず、好戦的なパーソナリティーの持ち主は、練りに練った手口や策略を駆使してとにかく人のうえに立とうとする。だから、そのやり口に通じていれば、攻撃と同時に相手の意図が見抜けるので被害を免れることもより容易になる。(略)
三番目の目的は、潜在的攻撃性などの人格の持ち主を相手にするとき、誰にでも効果的に対処できる方法を具体的に紹介する点にある。好戦的な相手との関係を見直すため、それに不可欠なルールを提案するとともに、自分自身の心の力を高める方法を詳しく説明する。相手のふるまいを正そうとするたび、こちらの気持ちが滅入るという自滅的な悪循環はこの方法を知ることで打ち破ることができるはずだ。
2013年に発行された『あなたの心を操る隣人たち』(訳書)を文庫化・改題したのが、この『他人を支配したがる人たち』(2014年発行)です。
この本は、私の「もっと早くに読みたかった本ランキング」の第1位です。なぜなら個人的な経験と瓜二つの(長い)エピソードが登場するから。当時、そんな言葉は一般的でなかったと思いますが、教育虐待を取り上げています。
その様子や心情を表している部分で、私が「うちと同じ!」と思った箇所をいくつかピックアップします。なお登場人物は父親のジョー、母親のマリー、娘のリサです。私はマリーと同じ立場でした(今は離婚済み)。
- 娘のためにジョーが努力を惜しんだことはない。数カ月前、娘がはじめてBと記された成績表をもって帰ってきたとき、心配のあまりリサは学習障害ではないかと教師に連絡した
- 娘の学力と心理状態を検査するため、ジョーは評判のクリニックに予約を入れることにした
- 「娘さんは自分をひどく追い詰めている」。カウンセラーにそう指摘されたのをジョーは思い返した。「娘さんの悪夢は親ごさんへの怒りを意味しており、とくに期待ばかりを押しつけるお父さんに対する怒りは激しいようです」。
- 翌日、ジョーは満面の笑みでふたりの前に現れ、問題の解決方法が見つかったと突然打ち明けた。そして、最新のコンピュータと学習ソフトを買い込んだことを家族に告げた。これなら毎日二、三時間、リサとふたりきりで勉強できるし、そうなれば成績も戻る。(略)カウンセラーが指摘するように、リサが自分に怒りを感じているのなら、親密な時間を毎日過ごすことでその問題も解決できるはずだ。
- 本人は心から娘の幸せを願っていると思い込んでいたようだが、じつは周囲に対して、娘の将来を熱心に案じる父親だと印象づけるために最善を尽くしていたのだ。そして、ジョーが心から望んでいたのは娘がもちかえるオールAという成績だった。
- マリー自身、胸のうちでは夫の理不尽に気がついてはいた。

うえぇぇぇ。イヤだ。イヤだ
本では最終的にマリーが正しい認識を持ち、対処法を見出すところまで描かれています。
私は同様の閉塞感漂う状況のただなかにいたときに、この知見にたどり着けませんでした……。原著は25年も前に発行されているのに!
以前の我が家のように教育虐待が疑われる家庭の方や、それ以外でも「マニピュレーター」にお悩みの方にご一読をおすすめいたします。こうした息の長い本には、それぞれの人に当てはまる記述があるはずです。
まとめ
他人の心を操ろうとする人を「マニピュレーター」と称し、その特性、手口、対処法を提示する。
★★★★★ (我が家にぴったり当てはまる状況が取り上げられていた)










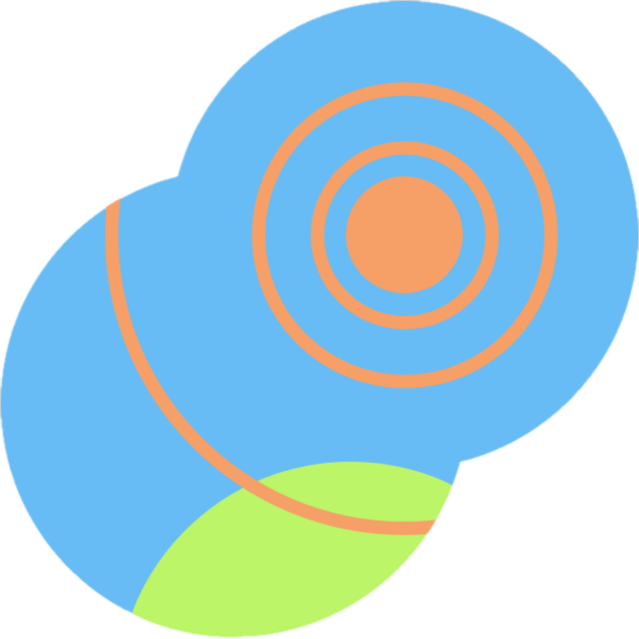
コメント