★★★☆☆
元家裁調査官が仕事を通じて実際に目にした「家族のしがらみ」を紹介しながら、心理学的な解説や解法を加え、さらに家裁調査官の仕事の内容にも触れる。
DV被害や離婚など、土台となる経験・知識があると楽しめる。
レビュー
この本の著者は元家裁調査官です。本の執筆時には大学の教壇に立つ一方で、臨床心理士・家族心理士としてカウンセリングを行っています。筆者が仕事を通じて実際に目にした「家族のしがらみ」を紹介しながら、心理学的な解説や解法を加え、さらに家裁調査官の仕事の内容にも触れています。
「家族のしがらみ」としては、夫婦間のものも親子間のものも、さらにそれらが絡まって世代間で連鎖したものも取り上げています。家裁調査官の仕事がそうしたものを扱うためです。
家裁調査官が所属する家庭裁判所は、大きく分けて家事部門と少年部門に分かれている。
家事部門は離婚から親権者、遺産分割問題などを扱い、(略)
少年部門は少年非行を扱っている。
ひとつひとつの事例、心理学的な分析、家裁調査官の仕事内容についての記述は、興味深いものが散見されます。その中で、私がそれまでに知らずにいて「へーっ」と思ったものを1つ挙げます。
児童虐待の実態があれば、児童相談所は子どもを保護し、虐待をしている親から引き離す。(略)しかしこれには予想外に困難な事態が立ちはだかることが多い。親が反対することがあるからだ。
(略)
児童相談所は残念ながら、親権者の意に反してまで子どもを児童養護施設に入れることは出来ない。それでも子どもの福祉のために、児童相談所が必要と考える場合には、家庭裁判所にその承認を認めてくることになる。(略)
ここで登場するのが家裁調査官だ。裁判官からの命を受けて、調査活動に入る。親に会い、子どもにも会い、状況を多角的に調査し、親権者の意に反してまで福祉施設に入れる必要があるかを徹底的に調べる。そうしてその結果は裁判官のもとへ報告される。

このような強権的な国の制度があることを知りませんでした。社会的にも、家庭内の問題には立ち入らない、という昔ながらの空気はあると思います。
私がお世話になった児相の相談員さんは、モラ夫に批判めいたことは一切言いませんでした。子供を救うには、最終的には母親である私が「どげんかせんといかん」と思いました。
この本は、ややとっちらかった印象です。エピソード、心理学的な分析、家裁調査官の仕事内容が、代わる代わる出てきて、それぞれがまとまった記述はありません。知識を得ようと思うなら本を隅から隅まで読む必要があります。目次もあまり頼りになりませんでした。
しかし、離婚調停で調査官と出会った私としては、よみものとして読む分には現実感を伴って興味深く読めました。離婚調停で子供の親権争いをしそうな方におすすめです。
まとめ
「家族のしがらみ」を紹介しながら、心理学的な解説や解法を加え、さらに家裁調査官の仕事の内容にも触れる。
★★★☆☆







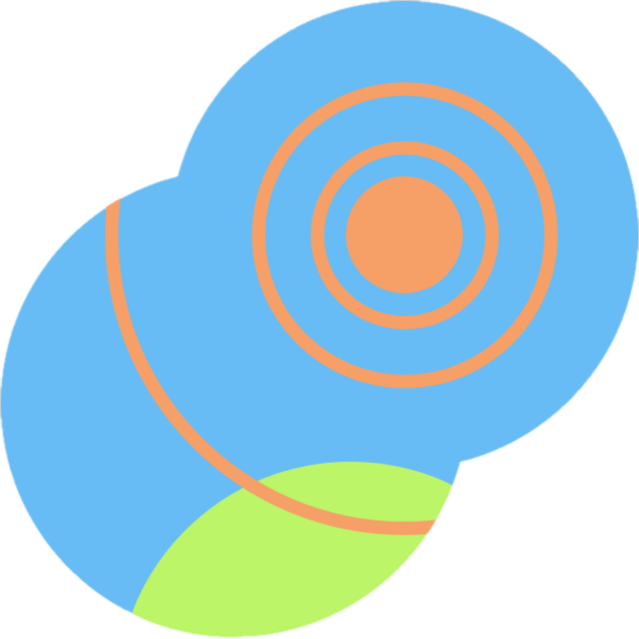
コメント