★★★★☆
DV・モラハラの被害者ではなく、根本原因の加害者に着目した本。
加害者向けの脱暴力プログラムの実態や、加害者が変わることの難しさが分かる
レビュー
この本は、日本で初めて「体系的なDV加害男性の暴力克服プログラム」に着手したカウンセラー(男性)が著しました。同プログラムは1997年に開始したそうです。意外なほど早い!
本の中ではDVの被害者ではなく加害男性(夫とか彼氏とか)に着目して、米国・日本における脱暴力の取り組みについての解説、著者ご自身による暴力克服プログラムの実態の紹介、社会への問題提起などを行っています。
目次は次のとおり。
- 序文
- 第1章 加害男性の背景にあるものと従来の対応
- 第2章 加害男性の暴力克服に関する新しい認識
- 第3章 加害男性の暴力克服支援の実際
- 第4章 加害男性の治療モデルによる個人心理療法の実際
- 第5章 もってほしい世界観の枠組み
- あとがき
DV・モラハラの被害者への各種の支援(カウンセリング、シェルター、等)って大切だし、私自身もお世話になってきました(相談体験)。被害者向けの本だって、ありがたく読んでいます(本一覧)。ただ、被害者へのアプローチって、ある意味、対処療法なんですよね。
この本が向き合っているのは、DV・モラハラの根本原因たる加害者のほう。著者の「暴力は加害者が生み出すのであり、被害者支援がいかに進展しても、加害者に何もなされなければ、DVは再生産され続けるのは明らか」という姿勢(以下)が反映されています。
素晴らしい! しかし著者はこの本で(別の本でも)苦境を語っています。以下、引用します。
筆者は加害者をなくす試みを通じてDV問題の解決に携わっているのだが、これは狭義の心理臨床というフィールドを超え、社会の認識を変え、さらに社会システムを変える運動の展開にまで踏み込んでいる。加害者への取り組みというのは社会全体を敵に回すに等しい、というのが筆者の偽らざる実感である。というのも、自分の問題に背を向ける加害者にとって加害プログラムの実践者は暴力を続ける価値観を揺るがす者だから不快なのである。また、加害者でない保守的男性層にとって暴力をふるうような男性は特別な男性で、自分とは無関係としておきたいがゆえに、自分と関係づける論理展開は深いだからである。また、加害者から徹底的に傷つけられた被害者とその支援活動に携わる人にとっては、尊厳を奪ってきた相手を大切にするように感じられ、許しがたい感情を呼び起こすからである。
発刊(2004年)から年月が経っているので、状況が改善していることを願いたい……。
DVに限らず、犯罪やいじめなどの加害者への対処法が、加害行為・加害者の正当化や自己防衛につながっちゃっているような措置・プログラムには、私も憤りを感じます。しかし、この本に書いてあることは、それと対局を成すものです。クソDV野郎のためではなく、被害者のためということが本から伝わってきます。
またたとえ専門家につながったとしても、人ひとりを脱DVへと向かわせるのは難しいんだな、と思いました。どうしたらウチのモラ夫・DV夫は変わるのか、あるいは変わらないのか、知りたい方には重大な示唆が得られます。
先鞭者の尽力に感謝しながら、私はこの記事を書きました。ぜひ、ご一読ください。
なお、ここで取り上げた『DV加害男性への心理臨床の試み』は、なかなかの読み応え。ひとまず基本的な情報を知りたい方には、同じ著者が同時期に発行した小冊子『ドメスティック・バイオレンス 新版――男性加害者の暴力克服の試み』をお勧めいたします。よろしかったら、以下からレビューをご確認ください。
まとめ
日米のDV加害者プログラムの歩みについて解説。著者が実施している脱暴力プログラムの紹介や、社会に向けての提言へ続く。
★★★★☆











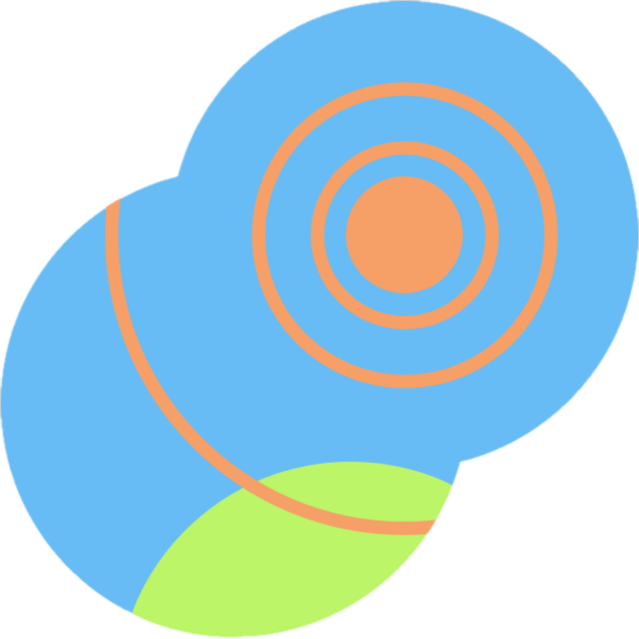
コメント